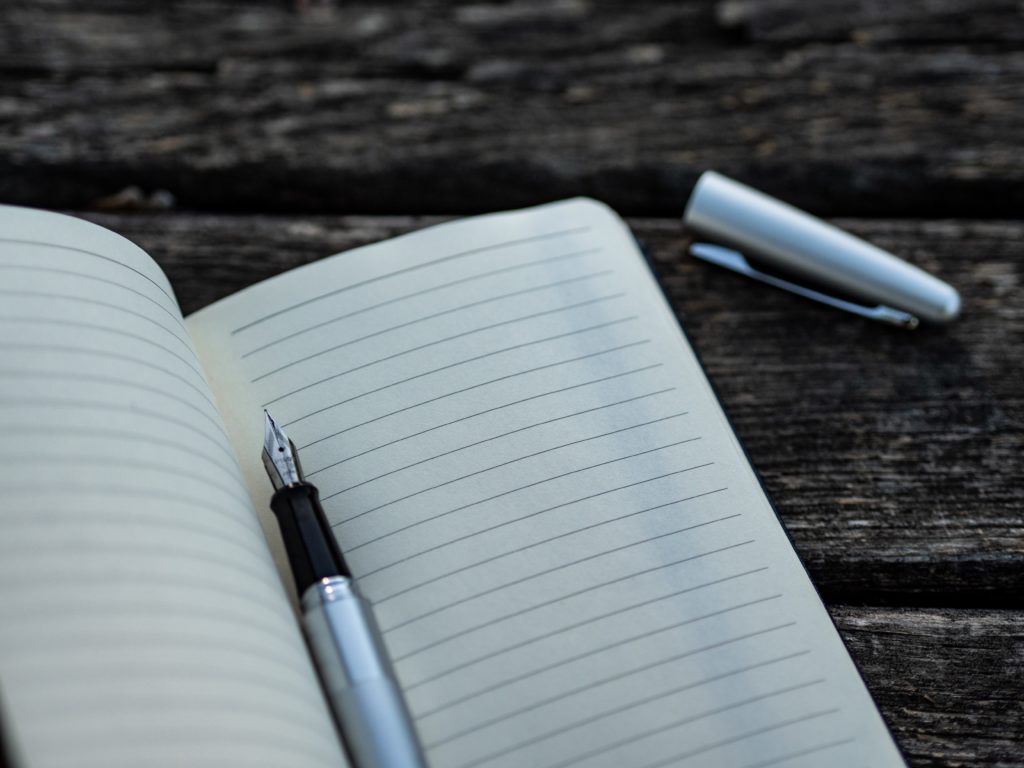こんにちは。EmiLia( エミリア)です。
6月といえば、ボーナスのタイミング。
自分自身の評価もあるけれど、課長として部下に評価を伝えるのも一つの大きなお仕事。
伝える役目
私自身は4月に課長になったわけで、前期の評価は前の課長がつけたもので、
わたしがつけた評価で無いけれど、なぜ、このひとにこんな評価がついてるの?と思ったり、評価が硬直的な部分があり、古き良き日本企業なのかと思ったり。
逆に、「評価されてこなかったんだな」とその差について考える人もいる。
一般論としてだけれど、全般として管理部門だと、
従順に無難にこなす方が評価されるのかも知れないと、その傾向を個人的に考える。
そういう忌で、営業など外からは、管理部門の体質として、保守的に変化しないものに映っているのだろうけど、それは評価が助長しているのだろうと思ったりもする。
賞与面談
それはさておき。
賞与の評価をひとりづつの部下に告げる「賞与面談」
勝手なこれまでのわたしの想像だけど、定年前で管理職でない方は、
どちらかというと「あがりの前に」こなしている印象を受けていて、
評価も半ば諦めているのかとこれまでのキャリアでは感じ取っていた。
先ほどのとおり、わたしは4月から課長になったので、
私の前任の課長がつけた評価を伝えるのが、今回の自分の役目。
私なりに20,30分時間をもらい、
ひとりづつ評価と期待することを伝えるけれど、
「なぜ評価があがらなかったのか?」とか、「なぜ下がったのか?」と食い下がられる人も1人ではなかった。
「もっと、その理由を説明してほしい」とか、
逆に「どうしたら評価を上げてもらえるのか」と。
自分の経験
私自身の経験を振り返ると、上司にそんなに時間を取ってもらい評価を説明してもらった経験もないし、同じように評価が高くなくても、うやむやな感じで、それを説明されたことはなかったので、上司と部下のやりとりは「こんなものなの?」と面食らうところもあった。
でも、「やる気がないのだろう」と思い込んでいた自分を反省し、「どうしたら評価を上げてもらえるのか?」とひとりひとりの問いについて、自分なりに答えてみた。
もちろん、相対評価の社内では、それをやってもらったとしても、評価を上げる保障はないけれど、少なくとも次回の評価をつけた結果を告げる際に、自分の言葉でできる限り説得性を持たせられるのだはと思う。
社長以外は、サラリーマンである以上、評価がつくのが多くの会社の仕組み。
自分のポリシーは、何歳になっても「輝く」というものなので、たとえ60歳前後でも、これから未来を切り拓く年齢でも、区別することなく仕事のアウトプットを期待し、それに対し、日々コミュニケーションをとっていこうと決めた6月の初旬の出来事を。
◼️合わせて読みたい
EmiLia
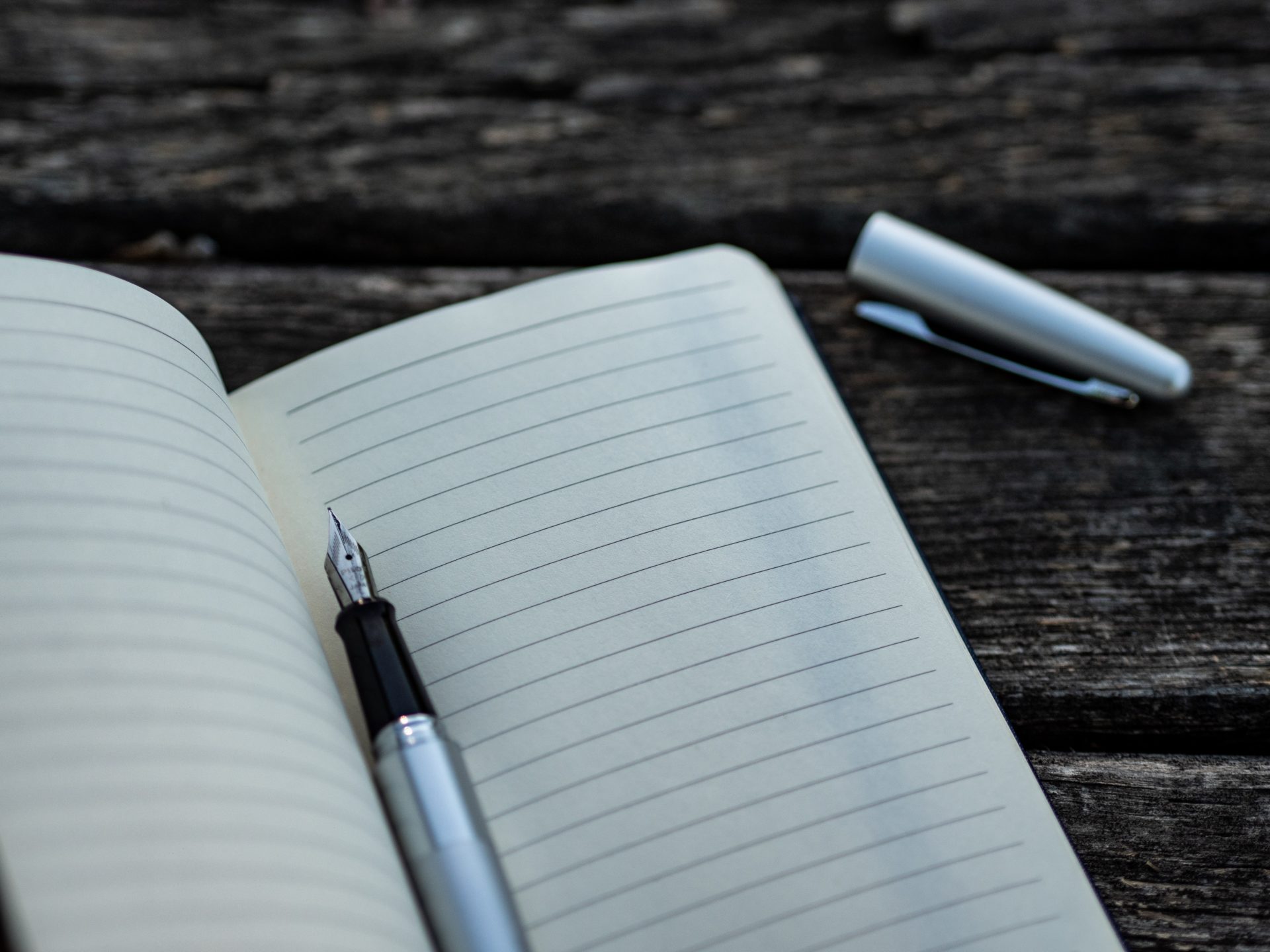

 e3lia.com
e3lia.com